
コロナ禍、戦争、環境問題をはじめとする「世界の問題を解決するために貢献したい」と考える学生はあなたを含め、近年非常に増えてきています。SDGsに代表される世界の諸問題の解決のための方向性を、単なるお題目に終わらせては地球の未来は無いでしょう。そのために学生の皆さんにできることは、問題の本質を深く理解し、そして解決への貢献が少しでも多くできるよう、自らを磨き上げることです。国際公務員をめざす人、環境ビジネスに関わりたい人、貧困問題を解決したい人など、世界のために働きたい人は世界の縮図のひとつであるアメリカの大学で幅広く、深く学んでみましょう。
国際関係学専攻の概要
アメリカの大学では、世界の問題を広い視点で捉え、国際的な諸問題の解決や国の安全・安定を考える学問として、国際関係学が設置されています。一方、特定の国や地域(例えば北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカなど)の歴史・経済的な問題にフォーカスし、問題解決や発展について考えるのが地域研究学です。これらはどちらも、複雑に絡み合う政治、経済、歴史、地理、文化人類学などをバックグラウンドの知識として学んだ上で、諸問題について考察を進めていきます。
どの方向に進むのが正解ということは無く、あなたの問題意識や知的好奇心に従って、どんどん掘り下げていくのが国際関係/地域研究学と言えるでしょう。その点で、アメリカの大学の環境は大きな助けになります。
圧倒的な講座数
アメリカの大学の特徴のひとつはその規模の大きさであり、それは講座数も例外ではありません。例えば受入大学のひとつ、アーカンソー大学では、歴史学だけでも約180講座もあります。実際にはこれらから自分の興味に合った講義を選択して受講することになりますが、これだけ細分化された授業を受けられる環境は日本ではなかなか見つけられないでしょう。
国際的な環境で学ぶ
アメリカの大学には中国、インド、カナダ、中東、アフリカなど世界からたくさんの留学生が集まります。世界の問題を考える上で、彼らと共に学ぶのは考え方の違いを理解する上でも、また相互理解のためにもとても大切なことです。実際に彼らと暮らし、時には冗談も言いながら世界の明日についてたっぷり議論してください。
例年夏には、さまざまな学生参加のキャンプやワークショップなどがワシントンD.C.やニューヨークをはじめとして全米各所で開催され、近年ではオンラインで世界の学生が参加する討論会なども開催されます。オンラインは便利な一方、交流要素はリアルイベントに負けますし、アメリカの他の地域に行くのも楽しみかつ勉強でもありますから、色々なイベントに参加してみましょう。
さらに、アメリカの大学からさらに他の国に留学することも推奨されていたり、大学によっては義務になっています。特に地域研究学の場合、研究対象の地域を実際に見聞せずにその地域を論ずることはできません。アメリカの大学にも交換留学の仕組みがあり、ヨーロッパや中国などアジア、南米、アフリカなど各地域に1学期〜1年程度の留学をすることが多くなります。

世界のことを勉強するのに、日本にこもっていては始まりません!やはり実際に見ることが大切です。
自分なりの組み立てができる
例えば貧困の問題に興味があり、経済について学んでいく中で、さらに深く学びたくなったら、経済学の履修単位数を増やし、副専攻(minor)にしたり、さらに伸ばして2つ目の専攻(Double Degree)にすることもできます。また別のケースで、IT技術をつけるため、情報システムについて学んでみるなど、自分の興味に応じて学びの方向や深さを自由に拡大していくことができるのがアメリカの大学の楽しい点です。また、各種インターンシップ(職務体験)を経験することも大切です。インターンシップは大学からの紹介の他、自分で探した企業・団体に依頼し、大学に承認してもらうというケースもあります。豊富な経験を積み、あなただけの国際関係学専攻を作っていきましょう。
学部卒業後の大学院進学も
国際関係学では、上記の通り幅広い予備知識をつけることもあり、大学によっては学士(学部)課程では予備知識習得を主目的とし、具体的な諸問題の本格的な議論・研究については大学院で取り扱う場合があります。また、例えば国際公務員となって国連を目指す場合は、修士号(大学院卒)を保持していることはほぼ必須条件です。進学の際には将来、大学院に行くことも視野に入れながら検討しましょう。

国際関係学は歴史や地理などを学ぶことで、「なぜ今、世界や地域はこうなっているのか」の理由を理解していくことが第一です。大学では、本を読み漁り、ガンガン議論をしていくことになりますから、まずはそれに耐えられるだけの英語力をしっかりつけましょう。NCNでは、国内語学研修を通じて、日本での準備段階から英語力を高めていく仕組みを作っています。
国際関係学専攻の卒業生の進路
国際関係学を学んだ学生の進路は、その中での専門・研究領域に応じて変わるでしょう。たとえばNCN学生のケースでは、以下のような事例があります。
国際関係学・卒業生の主な就職事例
・テレビ局報道部門で勤務後、大学院に進学、その後国連職員(国際公務員)に
・公務員試験を受験して国家公務員に
・大学院卒業後、国際問題のシンクタンク(研究機関)に就職
・政府系金融機関(日本銀行、政策金融公庫など)に就職
・民間部門からの国際貢献を目指して商社や都市銀行に就職
・国際的な仕事を求めて外資系企業や日本の大手企業に就職 etc.

上記は本当に私たちの卒業生の実績で、スタッフから見ても尊敬できる卒業生ばかりです。もちろん優秀な学生の例ではありますが、この分野は政治の議論ができるくらいの英語力と国際対応能力がつくだけに、もう少し平均に近い学生であっても、かなり強力な武器を持って社会に出ることになります。私たちもいずれ国や世界を動かせるような立派な卒業生をたくさん送り出したいです!
経済学をプラスしてアメリカで就職のチャンスを広げる
アメリカの留学生にとって、OPT(Optional Practical Training)とSTEM OPT Extension(STEM専攻者のOPT延長)は重要な雇用機会を提供するプログラムです。OPTは、卒業後に専門職の実務経験を積むためのプログラムで、通常は最大12か月の期間の米国での研修的な就労が許可されます。
一方、STEM OPT Extensionは、STEM分野(科学、技術、工学、数学)の学位取得者向けの特別な延長プログラムで、最大24か月の追加OPT期間を提供し、合計で最大36か月のOPTを可能にします。これらのプログラムを利用することで、留学生は卒業後に専門職の実務経験を積み、アメリカでのキャリアを築く機会を得ることができます。この間に、より実戦的な技術を身につけるともに、アメリカでの就職の機会を探すことができます。
一般的にはSTEMは工学やIT系のイメージが強い一方、実は国際関係学では、関連専攻の経済学もSTEMの対象となります。将来アメリカで働きたい人は、ダブルメジャーで経済学の学位も狙ってみましょう。
高校生向け特集ページ
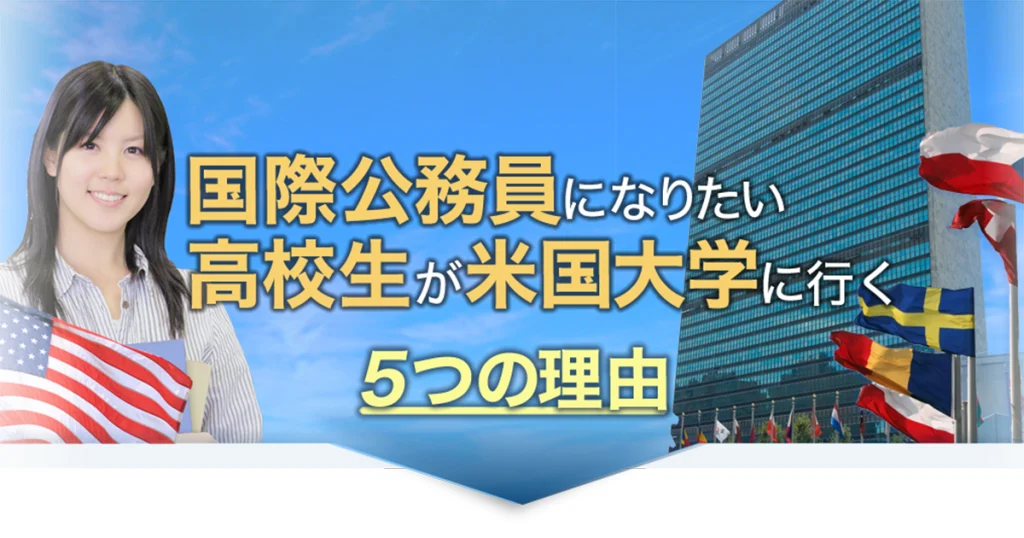
国際公務員になりたい高校生が米国大学に行く5つの理由
高校生向けにアメリカの大学に進学するメリットを5つのポイントにまとめました。本ページと合わせてご覧ください。詳細を見る
進学説明会のご案内

国際関係学専門の説明会を開催中
米国大学の国際関係学専攻や日本人学生受入制度について詳しくご説明する進学説明会を東京・大阪・オンラインで実施しております。詳細は以下のページをご覧ください。ご参加、ご相談は無料です。
国際関係・関連専攻
上記以外の関連専攻を挙げてみましょう。

環境学
環境学は、より科学的な視点から人間の活動による環境への影響の分析やその対応について考察する。理系学生にお勧めの専攻だ。

公共政策学
公共政策学は政治学より市民に対する政府のサービスなどにフォーカスしている。よりローカルに社会問題に向き合いたい学生にお勧めしたい。

ビジネス学
国際貢献は、何も政府機関や国連でなければできないものではない。一般的な経済活動から社会や国際貢献を行うという視点も持っておきたい。

経済学
貧困から戦争の原因に至るまで、国際問題の多くは、経済問題と切っても切り離せない。根本を学ぶという意味で経済学は押さえておきたい専攻だ。

文化人類学
文化人類学は、地域、民族、言語、宗教、習慣、価値観など文化そのものの流れや比較を扱う。これも世界の問題の解決には必要な知識の一つだろう。

データサイエンス
データサイエンスは、大量のデータを収集・分析し意思決定に役立てる情報技術と統計学の統合分野で、応用できる範囲は非常に広い。
国際関係の推奨大学
国際関係学専攻は、研究型大学から標準的な州立大学まで様々な大学に設置されています。ここではトップクラスの大学を紹介しますが、学力、成績、英語力などによって多様な選択ができます。詳しくは「専攻分野別進学説明会・国際関係学編」でご確認ください。
ネブラスカ大学リンカーン校/
University of Nebraska - Lincoln
国際関係の充実度がトップクラス
国際公務員をめざす学生にとって、最も条件の整った大学のひとつとして推奨するのがネブラスカ大学リンカーン校だ。同大学は、全米3500大学中62大学からなる最もプレステージの高い大学グループに、ハーバードやUCLAとともに名を連ねている。
学部課程と大学院を合わせて250近い専攻は、学際研究である国際研究学の背景としては理想的。国際研究学の指定科目はこの広汎な分野から200講座以上も揃っている。また、ジャーナリズム学では全米トップ10の評価を得ており、国際的な活動の可能性を広げる学びとして人気が高い。また、グループ大学でNCN特別奨学金実施大学であるオマハ校、カーニー校にも国際関係学が設置されており、これらの大学で実力をつけてから転学先として検討するのも良いだろう。

最近、バスケットボール日本代表の富永選手の在籍校として日本でも一気に有名になりました。この大学から名門ジョージタウン大学院に進学した先輩もいます。実力派におすすめです。



ジョージワシントン大学/
The George Washington University
首都ワシントンDCの三大有名大学
ジョージタウン大学、アメリカン大学とともに首都三大有名大学のひとつ。法学・政治学で高い評価を受け、大学院在籍学生数が学部学生数を上回ることが物語るように、専門性の高いコースに全米・世界から学生を集めている。そのキャンパスは国務省をはじめ政府機関・国際機関の並ぶ地域にあり、国際政治・国際経済の活動が散らす火花を身に受ける感覚で毎日の大学生活を送れるのは、国際公務員等をめざす学生にとって最高の恩恵と言える。ホワイトハウスのスタッフをはじめ、国際社会のトップで活動する人材を生み出し続けている。
トップスクールはの入学のハードルも高く、本機構でも共通審査の面接段階では確実に合格を保証できないチャレンジレベルの大学。また、生活費を含む年間学費も1,000万円前後(州立大は200万円台から)になるため、高度な専門段階を学ぶ場と考えて、学部レベルは州立大学で着実に学んで高い成績を取り、大きな奨学金が受給できるようなら大学院進学で狙うのも現実的な進路設計だ。

世界最高クラスの大学です!・・が、「日本で国公立を狙っているからアメリカもトップスクール」と安易に考えるのは危険!トップスクールは、言うならば「勉強の世界のワールドカップに出る」くらいの力が求められるチャレンジです。しかし、それだけに卒業できれば文句なくグローバルリーダーとして活躍できることでしょう。


ネブラスカ大学カーニー校/
University of Nebraska at Kearney
基礎から国際関係学を安心して学べる
ネブラスカ大学カーニー校は、上記のリンカーン校の姉妹校(ネブラスカ大学システム)で、標準的な州立大学です。NCN特別奨学金実施大学であり、学費が経済的で、基礎からしっかり学びたい、これから力をつけたい学生に最適の選択です。国際関係学には日本人の教授が在籍、留学生オフィスの担当を兼任されているため、初めての留学でも安心して学ぶことができるでしょう。標準的州立大学の中では関連講座がかなり充実しており、さらに転学を希望する際には、上位大学のオマハ校やリンカーン校に100%単位互換ができるため、予算を抑えたい学生にもおすすめです。

最初は転学を考えていても、結局卒業時までカーニーで学ぶ学生も多く、まさしく「住めば都」のとても良い環境の大学です。

国際関係学
専門の説明会を開催
分野別進学説明会・国際関係編
東京・大阪・オンラインで実施
この説明会では、国際関係学に特化して、アメリカの大学への進学・留学について詳細にご紹介します。世界一の環境、学びの流れ、国際公務員を含めたキャリアプラン、気になる費用など、世界への貢献をめざすあなたが欲しい情報をすべてお伝えします。また、個別相談のお時間も設けています。
詳しくは特設ページをご参照ください。
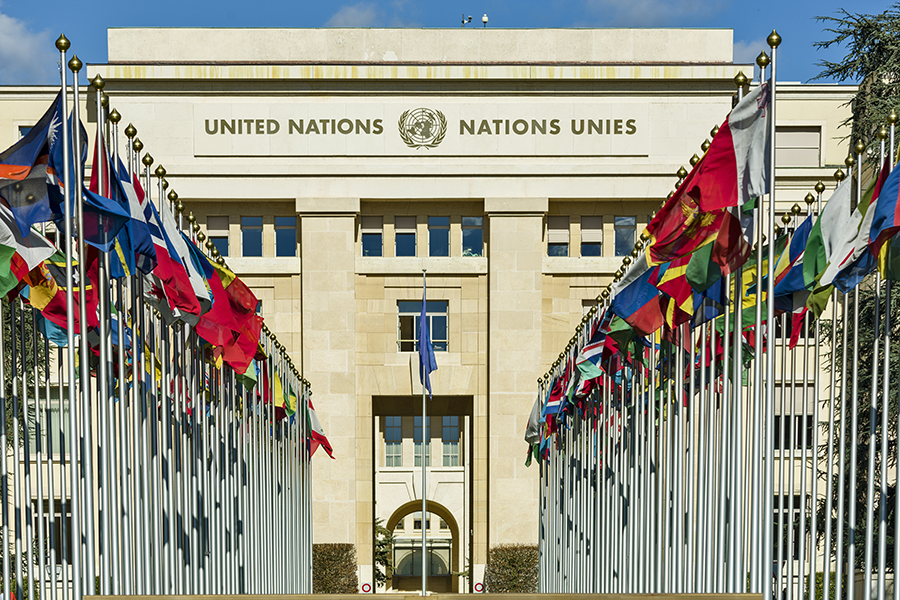
資料請求のご案内
日本人学生受入制度に関する
詳しい資料をお送りします
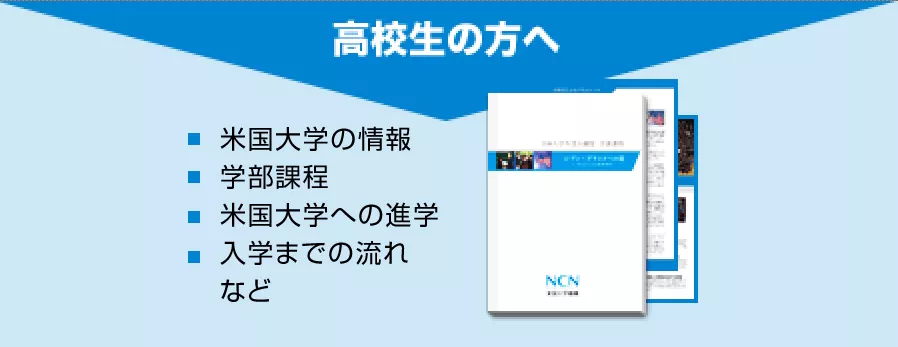
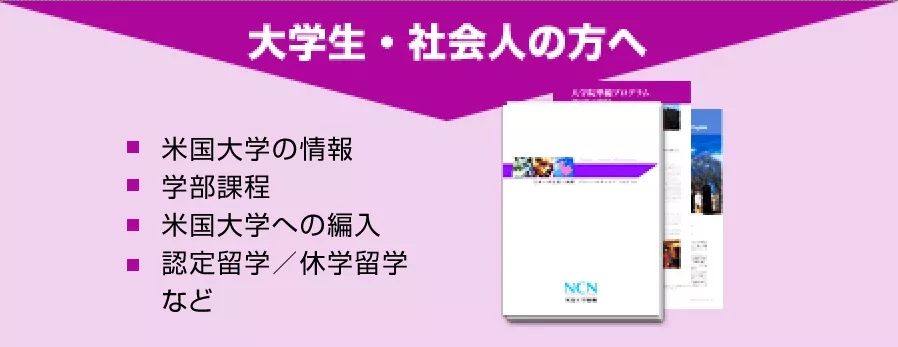
◎ チャットでも資料請求ができます。画面下のチャットウインドウより質問に従って情報をご入力ください。
他の専攻も見る
それぞれの分野については、通常の進学説明会でもご相談に対応するほか、「専攻分野別進学説明会」として各分野に特化した説明会を開催しています(全学年共通)詳しくは以下の各専攻解説ページをご覧ください。
※時期によっては直近の開催が設定されていない場合もございます。この場合は、高校生向け総合進学説明会/大学生・社会人向け進学説明会にご参加ください。
【航空学】パイロットになって大空を飛びたい
アメリカでは大学の中にパイロットの養成プログラムが専攻として設置されており、大学卒業とともに事業用操縦士のライセンスを取得できます。子供の頃からの空への憧れを、現実の進路に変えましょう。
【国際関係】世界の平和と幸せに貢献したい
止むことのない戦争や貧困、飢餓、災害。世界を襲う様々な危機に、自分が何ができるかを考え、必要な力をつけるためにアメリカで学べることはたくさんあります。
【映画・映像】映像・CGなどを本格的に学びたい
エンターテイメントの層の分厚さは、昔も今もアメリカは世界一です。米国大では本格的な映画から配信動画、ニュース、CG、VR/ARなど最新技術まで何でも学ぶことができます。
【スポーツ】スポーツの世界を支える仕事に就きたい
部活などでせっかく大好きになったスポーツに一生関わっていきたいという学生には、アメリカのスケールの大きな環境と細分化された専攻は最適な選択です。トレーナー、スポーツビジネス、報道など各種専攻を解説します。
【航空宇宙工学】飛行機やロケット、宇宙船の開発をしたい
航空宇宙工学は、航空機や宇宙関係、その他乗り物全般を含めて研究開発をするエンジニアを育成するための専攻です。アメリカ、日本、そして世界に通じる技術を身につけましょう。
【コンピューター・IT】現在と未来の中心産業で活躍したい
GAFAMに代表されるビッグテック企業が世界を牛耳る今、大学においてもこの分野は最も拡大に力が入っている専攻群です。科学からITビジネス、保守やセキュリティなど基盤を守る技術まで、自分に合うポジションを探しましょう。
【ビジネス】世界の最前線でビジネスを学びたい
世界のビジネスの中心、アメリカで学びたいという学生はとても多いはずです。ビジネス一般から金融、会計、起業など専攻分野としては多岐にわたります。ここでは、主なビジネス系専攻を紹介していきましょう。
【舞台芸術】ミュージカル・音楽・ダンスも専攻で選べる
ブロードウェイや世界で活躍したいというプレイヤー系、脚本、舞台装置や衣装、音楽ビジネスなどスタッフ系、どちらもプロの門を叩けるだけの本格的な内容をアメリカの総合大学で学べます。
【環境学】地球環境を守るために貢献したい
地球温暖化・資源問題など環境に関わる専攻はアメリカの大学に多数あります。また、理系的アプローチばかりではなく政治経済や国際関係からも貢献することはできるでしょう。
【医学・医療系】アメリカで最先端の医学を学ぶ
国際的な医師を目指したい、それもできればアメリカで先端医療を学びたいという高い希望を持っている学生の皆さんに向けて医学と、その他の医療系専攻について触れていきます。
旧・専攻解説ページのアーカイブ
下記のページで取り上げている分野については、総合進学説明会でご相談に対応いたします。また、記事も本ページや各種投稿にて最新版に更新していく予定です。
お問い合わせ
学生・保護者の方の
お問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ
[9:30-18:00] 年末年始を除く毎日営業
