トップスクールへの進学は、学力に自信のある学生にとっては頂点の進路として憧れるものでしょう。日本の受験の感覚では、学部入学時点でめざしたくなるものではあると思いますが、各州トップの州立大学から大学院でトップスクールに進学するという方法は、私たちのお勧めの方法です。この方法で、世界一有名なトップスクールのひとつ、ハーバード大学への進学を果たした卒業生の事例を紹介しましょう。
※この記事は旧サイトからのアーカイブ記事です。情報は収録当時のものとなりますのでご了承ください。

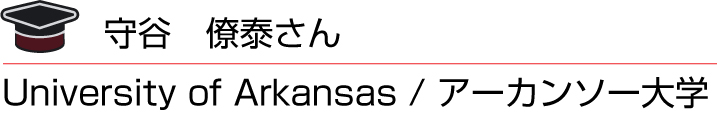
高1の頃からアイビーリーグに進学したかった
もともと、建築家をめざすきっかけになったのは?
中学生位から建築に興味を持ち始め、フランク・ロイド・ライトなどの美しい建築物を見るのが好きでした。高校1年生くらいには建築家になること、さらにアメリカの優れた教育システムで学ぶ、特にアイビーリーグの大学院まで進学したいということについては既定路線になっていたと思います。
まず、アーカンソー大学(UA)の建築学部の特徴を教えてください。
建築学にも様々なアプローチがありますし、中心的に教えられるデザイン・設計思想も大学によって違いがあります。UAにおいてはその土地の風土や文化を近代建築のデザインに反映させる「クリティカルリージョナリズム」という理念が主流です。他の大学では、例えば都市環境のあるべき理想像からひとつの建物を構築するやり方や、コンピュータを駆使してより複雑なデザインを志向したりと様々です。


学部での大学選びには理念の違いは影響するでしょうか?
それぞれの理念、思想は学習を進めていき、理解が深まるなかで次第に自分と合うかどうか考えるようになりますし、そこまでの違いが出るのは上級生であったり大学院レベルの話だと思いますので、高校の段階でそこまで考える必要は無いのではないでしょうか。
建築学のカリキュラム
カリキュラムはどのように進んでいきましたか?
最初の授業では、例えば木の柵やタイルなど、日常の中にある繰り返しの模様の写真を撮って、それをもとにスケッチを描き、建築デザインの基本の、“あるモチーフを何度も反復して使う”基本を学んだりしました。
中級以上になると、それぞれの授業が相互にリンクしており、授業で知識を得ながら、デザインスタジオでの作業においては複数の授業での課題をミックスした作品作りをしていました。あくまで核になるのはスタジオです。
全体の傾向としては、細かい技術論というより、発想をいかにして広げるか、逆に広げた発想をどう形に収束させるかという建築家・デザイナーとして何かを生み出すためのトレーニングが多かったように思います。
大学では、毎日どんな生活でしたか?
授業とデザインスタジオの往復でした。やはり一般に言われている通り、「建築学は一番寝ない専攻」というのはUAも同じで、特に課題の締め切り前になると、授業時間以外はだいたい昼前くらいから夜中の3時くらいまで毎日スタジオにこもって作業していました。
奨学金を得てハーバード大学へ
大学院進学には、どんな準備をしていましたか?
建築学の場合、9割くらいはポートフォリオ(大学で制作したものの作品集)の出来で決まります。教授と相談しながら自分の表現したい事や学びたい関心事を作品に落とし込み、簡にして要のポートフォリオを作る。この作業に半年くらいかかりました。あとは推薦状集めをしたり、エッセイも何度もダメ出しされながら、教授に見てもらいました。
大学も進学への支援をしてくれるんですね。
そうですね。成績優秀者(編注:評定平均が4段階で3.5以上の学生は成績優秀者として表彰される)に対しては、トップスクール進学のために色々なバックアップがあります。
なぜハーバード大学を受験しようと思ったのですか?
学ぶ中で各大学の特徴や有名な教授などの情報は入ってくるので、それに基づいてリストアップしました。しかし、実際有名教授がいると言ってもどのくらいの頻度で教えてもらえるのかということや、教授が他の大学に移籍した情報などはほとんどキャッチできないので、どちらかというと大学のカリキュラム上、自分の学びたい領域にマッチするかということのほうを重視しました。
実際、ハーバードの他にUCLA、ペンシルバニア大、イェール大、コロンビア大、プリンストン大を受け、UCLA、ペンシルバニア、コロンビアは合格しました。アメリカ以外ではスイス連邦工科大学も内容的に興味があったのですが、ドイツ語ができなかったのであきらめました(笑)。
他の大学は1年のコースだったのですが、ハーバードは2年コースだったため、入った後も興味に合わせて軌道修正できそうなのと、毎年20個くらいのスタジオ授業のオプションが選べ、かつ奨学金も年間100万円ほどですが出してくれました。また、自分のメインの研究課題である都市に関する研究が盛んで、世界の一流どころが集まるのも楽しみなので、ハーバードを選びました。
卒業後もアーカンソーで経験を積む
インターンなどは経験しましたか?
在学中ではなく、昨年5月に卒業後、OPT(卒業後にアメリカで1年実地研修ができる制度)でUA付属のデザインセンターと呼ばれる半官半民の組織で仕事をさせてもらえました。州都のリトルロック市の再開発計画のコンペ提出案を考えたり、研修といっても、新卒くらいの給与はもらえましたし、いちスタッフとして充実した日々を過ごせました。

今後の予定を教えてください。
5月より、日本の建築事務所で1ヶ月インターンの予定です。日本の建築業界にはオープン・デスク制度というのがあり、基本的に無給インターンですが雰囲気を知るには良いと思い、秋まではあと2つ位行ってみるつもりです。
建築学は、建築の論理を応用して全然関係のない他の分野のコンサルティングを行うなど、新しいことにも取り組む動きや、都市計画学や環境学など他分野との融合も進んできています。まずはハーバードで、また一段視野を広げて将来を考えていきたいと思います。
(2024追記)その後、守谷さんは有名建築設計事務所でキャリアを積まれ、2021年より独立して自らの設計事務所を開設、数々の作品を手掛ける傍ら、講師として日本の大学の教壇に立ち、後進の育成にもあたられています。
まずハーバードありきではない
守谷さんの場合、元々アイビーリーグに進学したいという希望はあったものの、まずハーバードありきではなく、学びたい方向と合致するからハーバードという選択であったというのが印象的でした。実際、知名度も大切な部分はありますが、各分野で「その道では超有名」という大学もありますし、何より自分の学びたい事を学べる環境が第一ということです。州でトップのアーカンソー大ですが、成績優秀でさらに上を目指す際には進路開拓を大学がバックアップするという方針があり、この点もアメリカらしい点で興味深いシステムです。
これらの受入大学からトップスクールへという進学プランについては、進学説明会で詳しく解説しています。
米国大学進学・留学説明会
東京・大阪・オンラインで実施
日本人学生受入制度の詳細は、進学説明会でご案内しています(無料・要予約)。詳細資料をもとに、受験方法や留学費用も含めた制度の説明を行うとともに、現地映像や学生インタビューも交えて情報満載でアメリカの大学をより理解していただける内容となっています。
親子で進路を考える機会としてぜひご活用ください。その他詳細は以下のリンクからご確認ください。


資料請求のご案内
日本人学生受入制度に関する
詳しい資料をお送りします
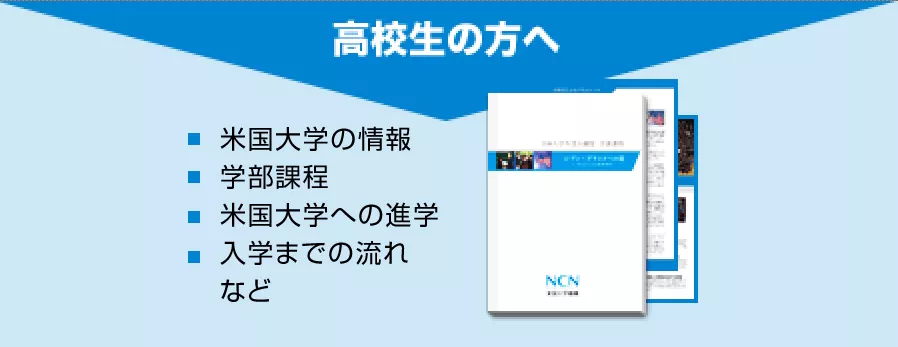
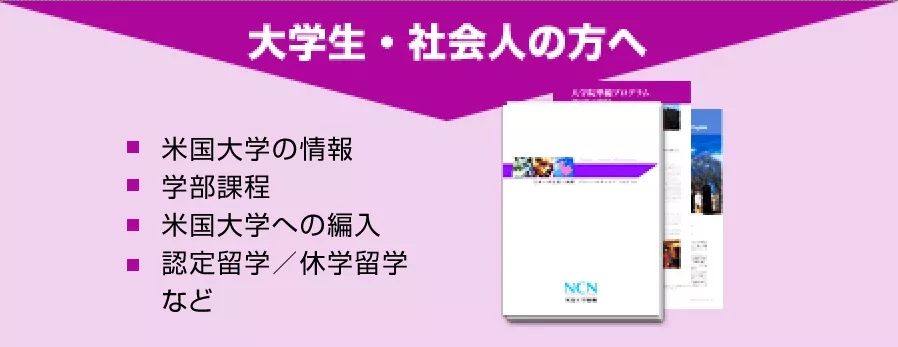
◎ チャットでも資料請求ができます。画面下のチャットウインドウより質問に従って情報をご入力ください。
お問い合わせ
学生・保護者の方の
お問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ
[9:30-18:00] 年末年始を除く毎日営業
